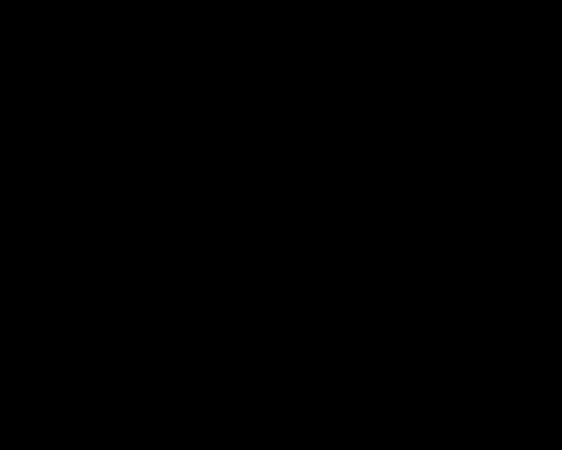いつまでも訪れない痛みに恐る恐る目を開くと、そこには思ってもみない光景が広がっていた。
蛮骨たちのところへ行く前にいた場所、あれほど帰りたいと願っていた現代だ。彼らと過ごした時間は十数ヵ月にもなるはずなのに、見ると戦国の世に行く前から少しも時間が経っていない。白昼夢と片付けるにはあまりにリアルな思い出に困惑するとともに、こうして帰って来たことを少しも喜べない自分がいた。
彼らはあの後どうなってしまったのか。大名たちの裏切りを受け、葬られてしまったのか。どうして裏切られなければならなかったのか。どうして、蛮骨はあれほど必死に庇ってくれたのか。
家に帰ってからも、彼らのことしか考えられなかった。何か手掛かりがあるのではないかと、何度も何度もあの小説を読み返してみたが、戻れる気配は無い。現実とも夢とも分からないことに入れ込み過ぎていると自身に言い聞かせつつも、消えてくれない胸の痛みに思わず涙が流れる。目を閉じて頬を伝うそれを指で拭うと、拭いきれずに雫となって落ちたそれが弾けて光った。
→
蛮骨たちのところへ行く前にいた場所、あれほど帰りたいと願っていた現代だ。彼らと過ごした時間は十数ヵ月にもなるはずなのに、見ると戦国の世に行く前から少しも時間が経っていない。白昼夢と片付けるにはあまりにリアルな思い出に困惑するとともに、こうして帰って来たことを少しも喜べない自分がいた。
彼らはあの後どうなってしまったのか。大名たちの裏切りを受け、葬られてしまったのか。どうして裏切られなければならなかったのか。どうして、蛮骨はあれほど必死に庇ってくれたのか。
家に帰ってからも、彼らのことしか考えられなかった。何か手掛かりがあるのではないかと、何度も何度もあの小説を読み返してみたが、戻れる気配は無い。現実とも夢とも分からないことに入れ込み過ぎていると自身に言い聞かせつつも、消えてくれない胸の痛みに思わず涙が流れる。目を閉じて頬を伝うそれを指で拭うと、拭いきれずに雫となって落ちたそれが弾けて光った。
→
出会い11