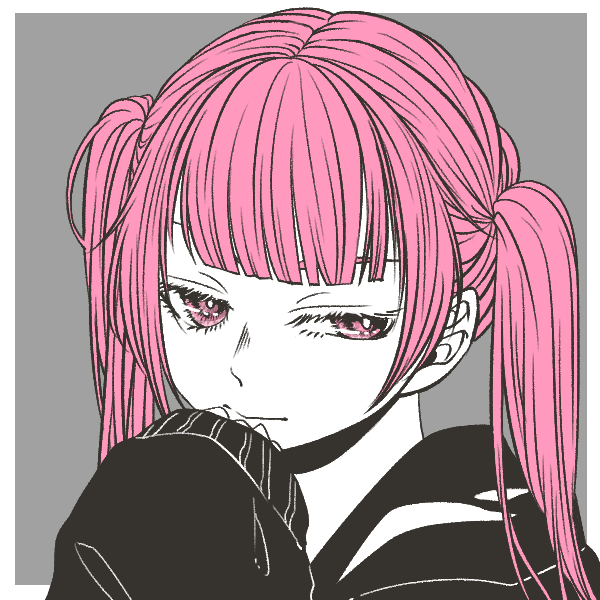いつもの公園⋯⋯ではなく、彼は家に居た。
寒さで凍りつきそうな冬の風にただ黙って耐えている。
彼が居るのは部屋の中ではなくベランダだ。
母親は連れ込んだ男と盛り上がり、楽しそうな声で笑っている。
これは今に始まったことではない。
いつもなら彼は男が来る前に家から出て行くのだが、タイミングを逃すと強制的に母親にベランダへと追い出されてしまうのだ。
最初は彼も抵抗していたが、母親の男に見つかると暴力を振るわれ続け、段々と抵抗するのも考えるのも億劫になり、ただ黙って従っていた。
一時は母親共々殺してやろうかとも考えたが、彼は亡き母方の祖母が好きだった。
誰よりも自分を大切にしてくれた祖母を思うとその娘である母には手を出せない。
昔は優しかった母も最愛の夫が亡くなってからというもの、心が壊れ、男遊びをするようになってしまった。
母親の中でもう自分は邪魔な存在でしかないのだと気づいてしまった今では怒りさえ冷めてしまった。
疎まれて恨まれて蔑まれるのは家でも外でも変わらない。
このまま黙って死のうかとも頭を過っていたが、ひとつの存在が思い出された。
公園で話していた人物の存在を。
彼はベランダを支えている柱を伝って滑り降りる。靴もなく、足や手には擦り傷を作りながらも何とか降りると公園へと向かう。
やっと公園にたどり着いたかと思えば、彼の視界はゆらゆらとしてまともに物を見ることさえできなくなっていた。
彼は公園の入り口の前でそのまま倒れてしまう。
──まあいいか。このまま死ねば苦しさから解放されるし。
彼が意識を失う間際ぽつりと呟かれた言葉はこれだった。
寒さで凍りつきそうな冬の風にただ黙って耐えている。
彼が居るのは部屋の中ではなくベランダだ。
母親は連れ込んだ男と盛り上がり、楽しそうな声で笑っている。
これは今に始まったことではない。
いつもなら彼は男が来る前に家から出て行くのだが、タイミングを逃すと強制的に母親にベランダへと追い出されてしまうのだ。
最初は彼も抵抗していたが、母親の男に見つかると暴力を振るわれ続け、段々と抵抗するのも考えるのも億劫になり、ただ黙って従っていた。
一時は母親共々殺してやろうかとも考えたが、彼は亡き母方の祖母が好きだった。
誰よりも自分を大切にしてくれた祖母を思うとその娘である母には手を出せない。
昔は優しかった母も最愛の夫が亡くなってからというもの、心が壊れ、男遊びをするようになってしまった。
母親の中でもう自分は邪魔な存在でしかないのだと気づいてしまった今では怒りさえ冷めてしまった。
疎まれて恨まれて蔑まれるのは家でも外でも変わらない。
このまま黙って死のうかとも頭を過っていたが、ひとつの存在が思い出された。
公園で話していた人物の存在を。
彼はベランダを支えている柱を伝って滑り降りる。靴もなく、足や手には擦り傷を作りながらも何とか降りると公園へと向かう。
やっと公園にたどり着いたかと思えば、彼の視界はゆらゆらとしてまともに物を見ることさえできなくなっていた。
彼は公園の入り口の前でそのまま倒れてしまう。
──まあいいか。このまま死ねば苦しさから解放されるし。
彼が意識を失う間際ぽつりと呟かれた言葉はこれだった。